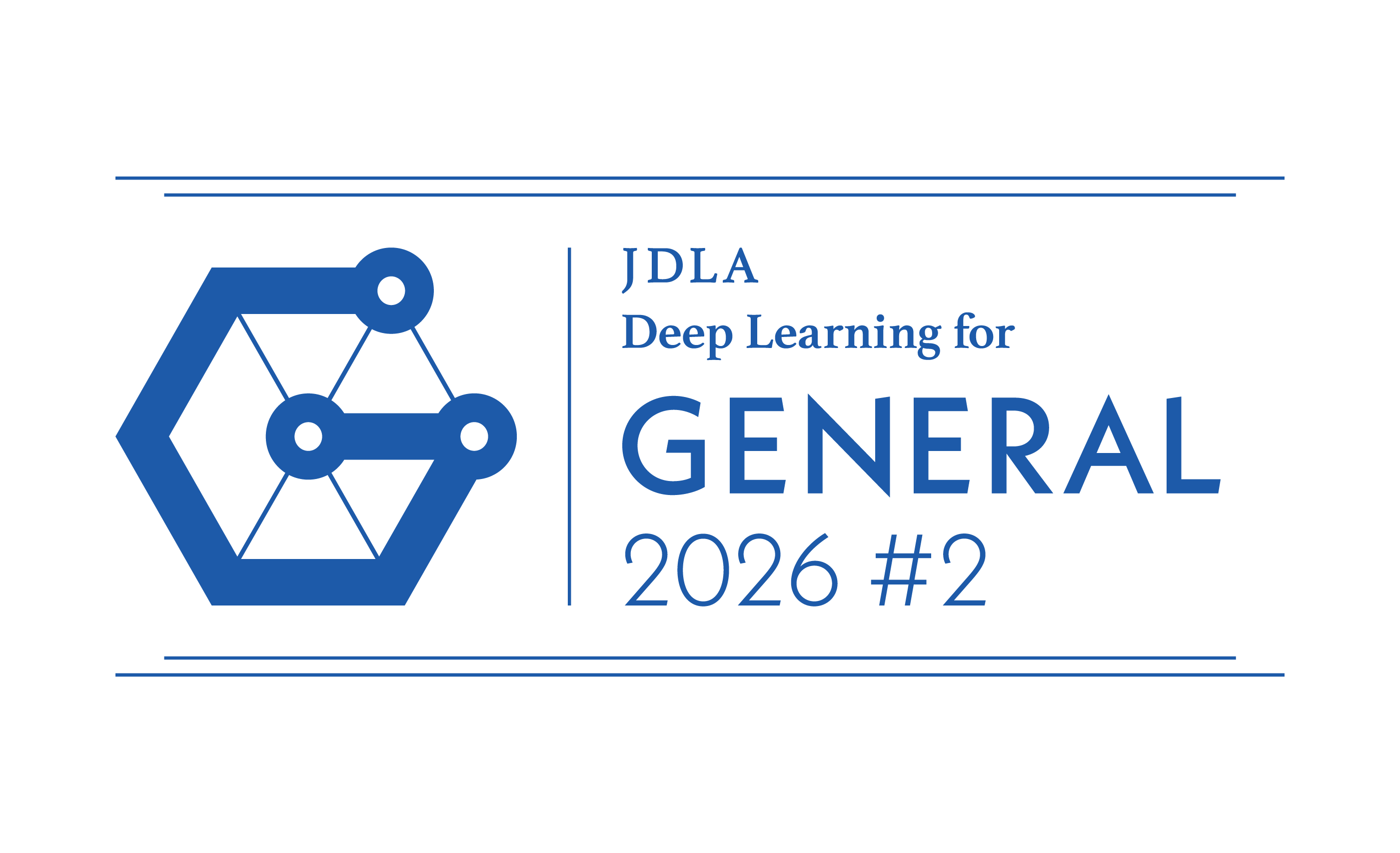AI関連技術が目まぐるしく変化する中、市場変化や競争スピードは激しさを増しています。特に近年では、生成AIの出現により、さらにそのスピードは加速。不確実性が高まる現状において、どの企業にでも「DX推進」は、自社の企業価値の向上に向けた喫緊の課題として優先的に取り組んでいることでしょう。
日本企業のDX推進を実現するためには、デジタル人材の確保は欠かせません。今回は、日本ディープラーニング協会(JDLA)理事であり、株式会社zero to one 代表取締役CEOでもある竹川 隆司氏にデジタル人材の採用や育成のポイントについてお話を伺いました。

デジタル人材の定義とは

デジタル人材とは、経済産業省が示す情報などを参考にすれば、”AIやIoTなどの先端デジタル技術を駆使し、社会や顧客に対して新たな価値を提供する”ことが可能な人材といえるでしょう。
具体的に、デジタル人材には、主に下記のスキルが備わっていると理想的です。
● デジタルリテラシー: デジタル技術の基礎を理解し、業務に活用する能力
● ビジネススキル: 顧客視点で課題を把握し、解決策を描く能力
● ソフトスキル: 目標達成に向け、関係者と協働し、説得・調整しながら推進する能力
デジタル人材には、AIなどの技術的なスキルだけでなく、業界知識やビジネス知見、コラボレーションのためのスキルも必要です。企業がDX推進を成功させるためには、これらのスキルを持った人材が欠かせません。
デジタル人材の重要性が増している理由

不確実性が高く変化の激しい経済状況において、企業は常に「新しい価値」を創造し続ける必要があります。さらに、既存のシステムに精通した人材の退職に伴うブラックボックス化いわば「2025年の崖」といった課題にも対応しなければなりません。
参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~/経済産業省
これまで以上に複雑化した企業を取り巻く環境の変化に対応するためにも、デジタル人材の重要性が増していることに間違いありません。
企業の競争力を保つため
ITやAI技術の急速な進化により、新規事業や起業のハードルは大幅に下がりました。消費者の価値観は多様化し、グローバル市場への参入も容易になっています。特に、SNSを通じた情報発信が消費行動に影響を与える傾向が強まり、消費者ニーズの変化スピードは加速しています。
欧米を中心に、ITやAIを活用した新たなサービスが次々と生まれる一方で、日本は依然として遅れを取っている可能性があります。
このような環境下で企業が競争力を維持するには、新しい価値の創造が不可欠です。市場や消費者がデジタル技術に迅速に適応する中、企業もデジタル技術を活用し、新製品・新サービスの開発やビジネスモデルの変革を進めることが不可欠です。
デジタル人材が不足している現状

そもそも日本では労働人口自体が減少しているため、デジタル人材の不足も例外ではありません。デジタルスキルを持つ人材の需要も高まる中、供給が全く追いつかず、「不足感」が生じているのが現状です。
特に国内ではデジタル人材の育成が十分に進んでおらず、新たな技術の登場に対して積極的に(貪欲に)キャッチアップする姿勢が求められます。継続的に新しいスキルを身につけ、成長を続けることが、デジタル人材を含む幅広い人材不足の解決につながるでしょう。
多くの企業がDX推進に向けてデジタル人材の確保に努めていますが、その難易度は年々高まっています。(独)情報処理推進機構の「DX動向2024」によれば、従業員規模300人以上1,000人以下の企業の60%以上が「DXの戦略立案や統括を行う人材が不足している」「DXを現場で推進、実行する人材が不足している」と回答。このような統計結果からも、デジタル人材の不足が深刻であることが明らかです。
デジタル人材を確保する方法

デジタル人材を確保する方法は、大きく分けて「既存社員の育成」と「外部からの採用」の2つがあります。
外部採用では、即戦力となるスキルを備えた人材を確保できる可能性がありますが、日本の雇用市場は流動性が低く、難航する可能性もあります。一方、社員育成では、必要なスキルセットを明確にし、継続的な教育・研修プログラムを充実させることが重要です。どちらの方法も一長一短があり、企業の状況に応じた戦略的な対応が求められます。
外部人材を活用・採用する
外部人材の活用や採用には、例えば次のような方法が想定されます。それぞれにメリットやデメリットがあるため、自社の方針や目的に応じて適切な選択を行うことが重要です。
- 中途採用: 長期的に活躍できる人材を正社員として雇用。企業文化への適応や継続的な成長が期待できるが、必要なスキルや適性を事前に明確にしておくことが重要。
- 派遣契約: 特定のプロジェクトや期間に限定して派遣契約にて人材を確保。即戦力として活用できるが、契約範囲外の業務を任せることは難しい。
- 外部アウトソーシング: 業務を外部の専門業者に委託。自社のリソースをコア業務に集中できるが、委託した業務についての社内でのノウハウ蓄積が難しくなるケースが多い。
- フリーランス: 業務委託契約を結び、特定のスキルを持つフリーランスを活用。短期間かつ柔軟に契約が可能な一方、機密情報の管理や契約途中での業務継続リスクに注意が必要。
社内人材を育成する
社内人材の育成には、主に次の3つの方法があります。それぞれの育成方法を通じて、社員のリテラシー向上を促し、組織全体の成長に繋げることが可能です。ただし、研修後も社員ひとりひとりが継続的に学び、成長を続ける意識を持つことが何より重要です。そのため、学習機会の提供や最新情報の共有を継続的に行うことが望まれます。
- 教育・研修プログラムの実施: 社内外の専門家を招き、研修やトレーニングプログラムを組む。オンラインを活用し、柔軟な学習環境を提供することも有効。
- OJTによる実践経験: 知識やスキルを職場で実践しながら学び、経験を積む機会を提供。
- リスキリングの推進: 将来の需要や現職で必要なスキルを再習得させるリスキリングも重要。最新のデジタル技術や専門知識を学ぶ講座への補助など。
デジタル人材採用のポイント

デジタル人材を外部から採用する際は、採用後の環境整備を十分に行わなければ、ミスマッチが生じる可能性があります。せっかくアンテナが高い優秀な人材を採用できても、伝統的な組織風土の影響でその力を十分に発揮できなければ、企業にとって大きな損失になり得ます。デジタル人材の採用を成功させるためには、以下のようないくつかのポイントがあるかなと思います。
必要なデジタル人材のスキルや要件を明確にする
外部から人材を採用する際、スキルや資格等の要件を整理することは当然ですが、デジタル人材の場合はより詳細な検討が求められます。デジタル人材とは、前述のとおり技術だけではなく、業界知識やビジネススキル、ソフトスキルを兼ね備えた人材を指し、経営企画室、DX推進部など部門横断的な部署へ配置される場合が多いです。
適切な採用基準を設定するには、採用側が事業との関連性を整理し、デジタル分野への理解を深める必要があります。採用を希望する部署と密に連携し、人材要件を具体的に策定することで、企業の戦略に合ったデジタル人材の確保が可能になるでしょう。
デジタル人材が働きやすい環境を整える
優秀なデジタル人材を採用した後のフォローは極めて重要です。日本企業ではAI活用やDXが進みつつありますが、多くの企業では関連部署や役割が比較的新しく、業務推進の知見が十分に蓄積されていないのが実情です。特に、AI技術の進化は早く、新規事業の推進過程で試行錯誤や失敗が生じることは避けられません。
デジタル人材の活躍を促すには、「失敗」を許容し、挑戦し続けられる環境が不可欠です。たとえば、AI戦略を推進するための部署を新たに設置し、そこでAI技術を活用した新規事業を小規模に始めていくなど、外部から採用した人材に「肩書」や「権限」を付与するのも一案だと思います。
もちろん、適切なルールや規律は保ちつつ、リモートワークやフレックス制度など働きやすい環境を整備することも欠かせません。これは、外部から加わったデジタル人材のみならず、既存の社内人材の活力を上げることにもつながるはずです。
リファラル採用なども活用する
人材採用のアプローチは多様化しており、従来の求人掲載に加え、リファラル採用やダイレクトリクルーティングも注目されています。特に、デジタル人材には、業界知識やビジネススキルに加えてソフトスキルも求められるため、社内のネットワークを活用したリファラル採用は、信頼性の高い人材を見つける上で有効です。
また最近では、SNSを活用した採用も増えており、自社の魅力や企業文化を発信することで、関心を持ってくれる人材に直接アプローチすることが可能です。このように、複数の採用方法を柔軟に組み合わせながら活用することで、競争の激しい人材市場においても、理想的な候補者を見つけられるかもしれません。
デジタル人材育成のポイント

自社の社員にデジタル人材としての育成機会を提供することで、個々の成長を促すことができます。特に、外部から採用が難しい場合、社内人材の育成は有効な手段となります。また、外部採用した場合でも、AI技術やデジタル領域は変化し続けるため、常に「成長」を促進するための仕組みは不可欠です。以下の人材育成のポイントも参考にしていただきつつ、仕組みづくりを進めてください。
スキルマップを活用し適正のある人材を選抜する
デジタル人材を的確に育成するためには、社内での明確な定義が不可欠です。まず、業務や職種を整理し、必要なスキルを可視化する「スキルマップ」を活用するとよいでしょう。可能であれば、各職種に必要なスキルセットと報酬体系を結びつけることで、より実践的な指標となります。また、スキルマップは研修計画の策定や教材開発にも役立ちます。
また、新規事業や研究開発部門に限らず、営業や開発などあらゆる部門において必要なデジタルスキルを整理することが重要です(例:セールスならデジタルツールの利用、開発ならAI実装スキルなど)。整理する際には、経産省が示すデジタル人材の定義などを参考にしつつ、各企業が独自の視点を加えることが求められます。
学習のための環境を用意する
デジタル人材の育成には、研修実施や資格取得の奨励など、個人が学べる「場」の提供が重要です。特に、研修計画を策定する際には、何を学べば競争力やモチベーションの向上につながるのかを整理する必要があります。また、資格取得に向けた学びを通して、体系的な知識やスキルを身につけることも期待できます。
研修や資格取得後のフォローアップも欠かせません。AI技術の進展はスピードが早く、少し前の正解がすぐに誤りになるほどの変化もあり得ます。こうした環境に適応するためには、成長を続ける姿勢が求められます。学習環境として、個々の成長をサポートする体制を整えることが重要です。
何より、デジタル人材は、自ら自発的、継続的に学習することが不可欠です。会社が決めすぎて社員の自発性が失われないよう、個人が学びたいときに学べるような機会を整備することも意識してください。
外部研修やeラーニングなども有効に活用する
自社内で独自の研修を開発することも一案ですが、デジタル領域の変化は早く、最新の内容に更新するには多くの時間を要します。更新作業に多くの貴重な社内リソースを割くよりも、専門性の高い外部研修やeラーニングを活用するのも効果的です。外部研修は、育成の知見やノウハウも豊富なことが多く、網羅的かつ実践的なスキルの習得が期待できます。
近年、デジタル人材育成のための外部プログラムが増えてきており、一定のカスタマイズも可能になっています。育成したいスキルや目的を明確にし、自社にとって効果的なプログラムを活用するとよいでしょう。
また、外部サービスを活用することで、今まで自社での研修や教材開発に要していた時間を、例えば人材活用の施策検討などより重要なタスクに割くことができるようになります。外部リソースを柔軟に活用しつつ、デジタル人材の育成と活用・フォローをバランスよく進めてください。
「G検定」ならデジタル人材育成の役に立つ
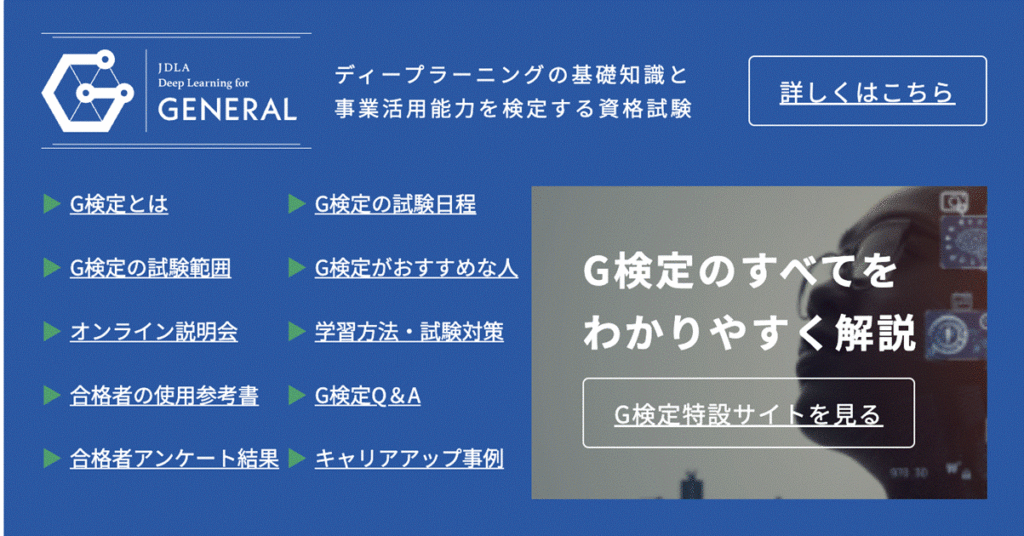
<参考:https://www.jdla.org/column/dx-skillmap/>
G検定とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、人工知能(AI)やディープラーニングに関する総合的な知識や活用能力を習得できる検定試験です。デジタル人材育成の入口として「G検定」は適切な資格のひとつだと言えるでしょう。
既に多くの企業や組織が業種や規模を問わず、G検定の受験を推奨しています。AI技術の体系的な学習を通じて、実務に即した知識を身につけることができると評価されているからです。
ただし、デジタル人材の育成はG検定取得で終わりではなく、むしろスタートですらあると考えています。G検定をきっかけに継続してデジタル技術に関し「学びを続けていく」ことが重要であり、学習習慣を定着させる手段として資格試験の活用は有効であるといえます。
・まとめ

デジタル人材は、企業のDX推進に不可欠です。デジタルスキル、ビジネススキル、ソフトスキルの3要素を備えた人材の確保と育成は、労働人口の減少が進む中でますます重要になっています。そのため、外部人材の採用や社内教育プログラムの充実がカギとなることはいうまでもありません。
人材育成の手段の一つとして、G検定などの資格取得は、個人が継続的に学び、成長するきっかけになります。社内で自発的に学び続ける人材を見出し、その成長を支援することが、自社のDX推進を加速させる近道となるでしょう。