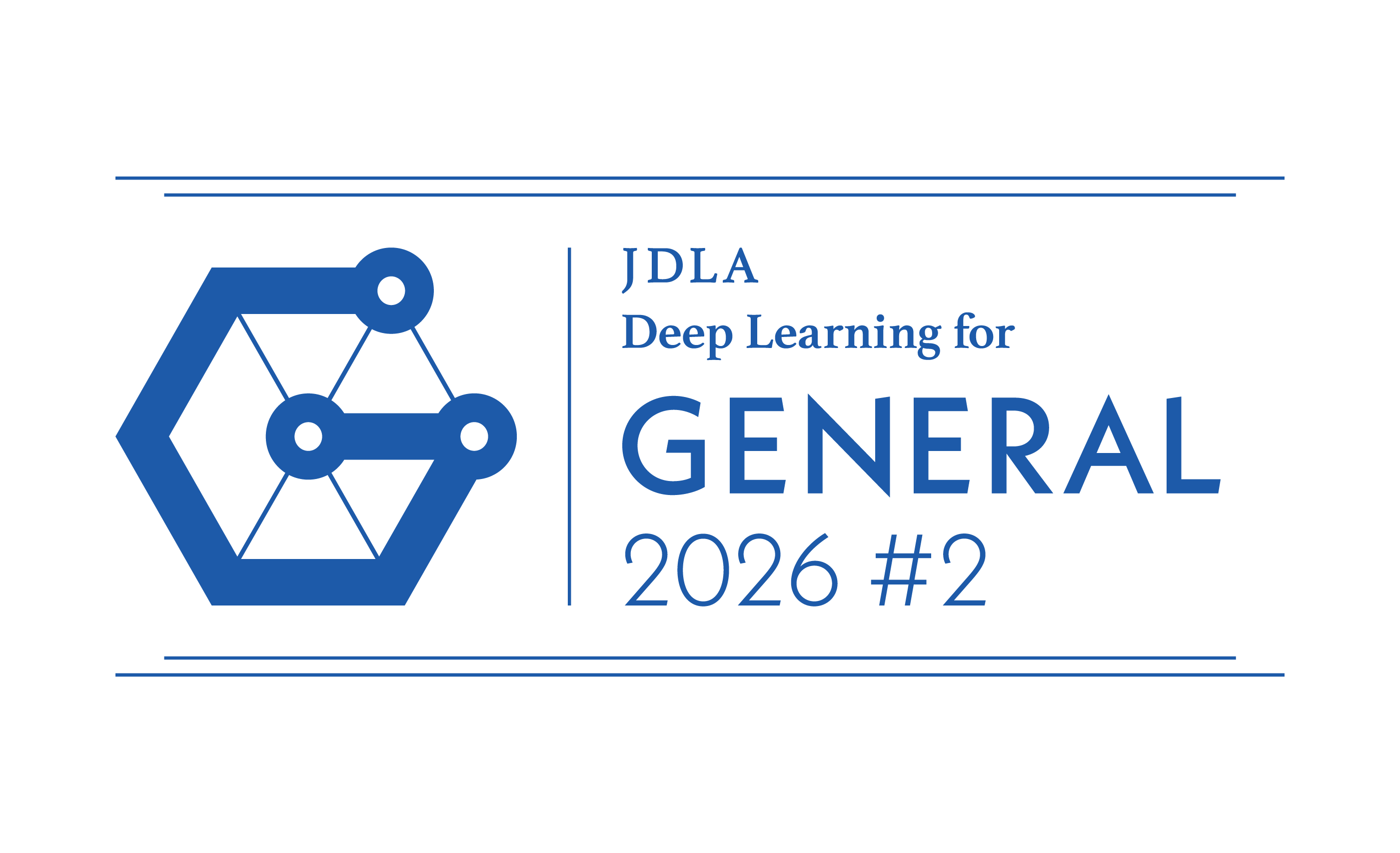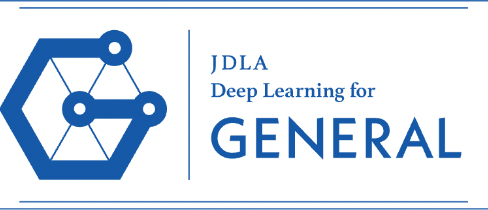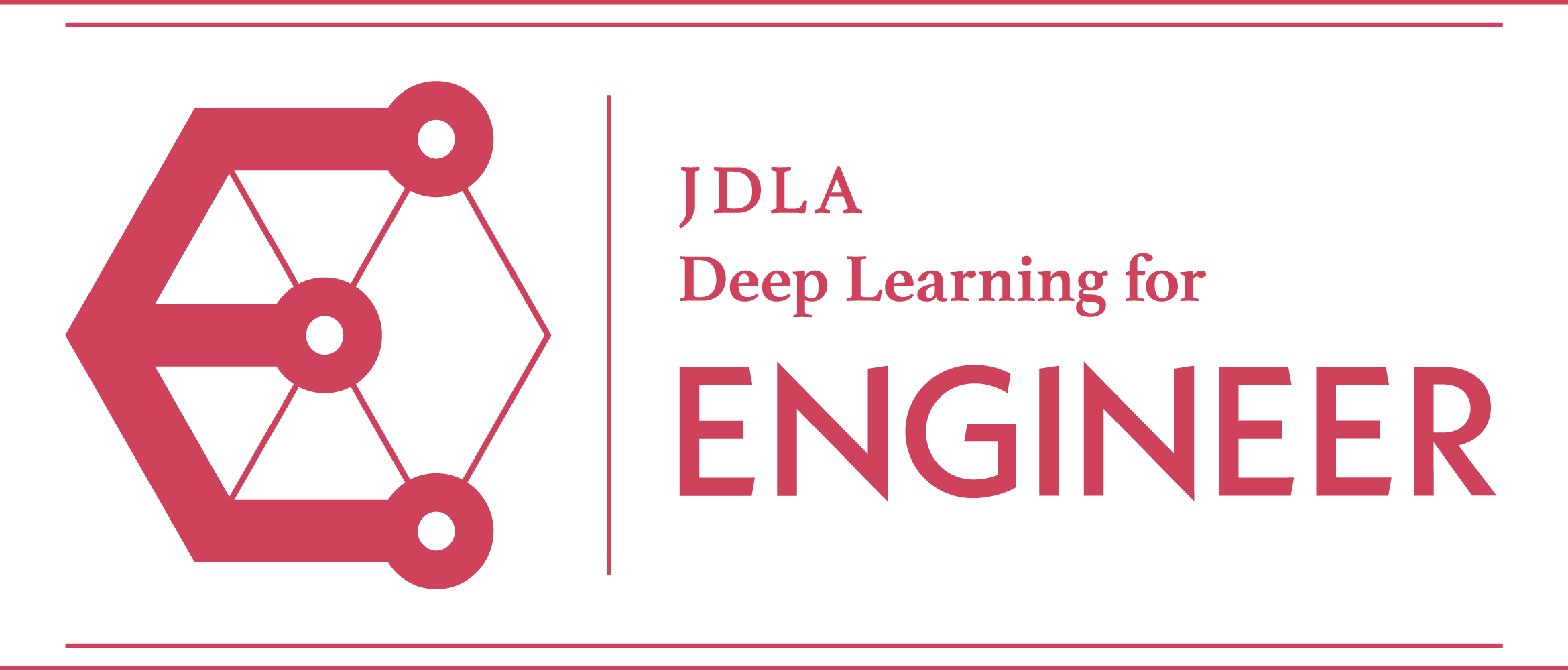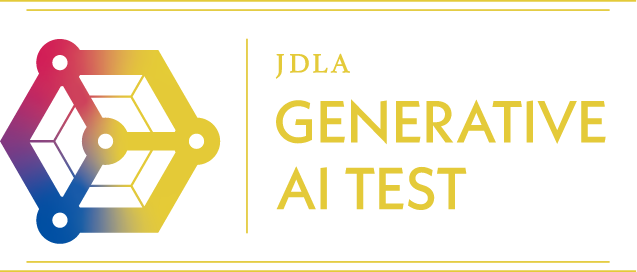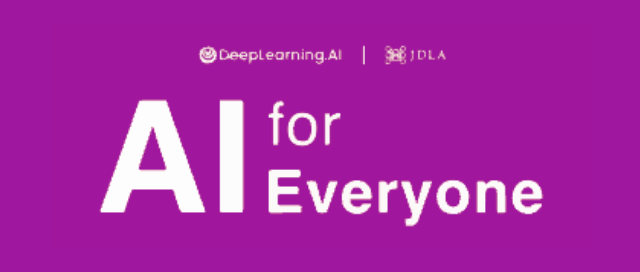三谷忠照社長は、シリコンバレーでの起業経験を経て、2017年に三谷産業株式会社の代表取締役社長に就任。同社は石川県金沢市に本社を置き、96年の歴史を持つ複合商社です。現在では6つの事業セグメントを展開しつつ、『創業90年を越えるベンチャー企業』として、AIを積極的に活用した変革を進めています。
AI活用を経営戦略の中心に据えた三谷産業株式会社の三谷忠照社長に、G検定を社員に奨励する背景、組織としての変化、そして未来への展望について伺いました。
プロフィール:
三谷産業株式会社 代表取締役社長
三谷 忠照氏
2023年を『AI元年』と位置付け、経営改革に挑む三谷産業

-2023年を「AI元年」と位置付けた理由を教えてください。
三谷氏 タイミングとして、ディープラーニングやAI技術への関心が高まっていたことが大きなきっかけでした。最初に全社向けに話をしたのが2022年の11月でした。2023年の1月頃から「AIに取り組もう」と本格的に発信し始めましたが、もっと前からその必要性を感じていました。「AI元年」という言葉を使うことで、一過性のトレンドではなく、会社としてAIに本格的に向き合う姿勢を明確に示したかったのです。
ただ、どのような結果がもたらされるかは予想がつきませんでした。特に、仕事の仕方がここまで大きく変わる実感を1〜2年のうちに得られるとは、全く想像していませんでした。しかし、業務効率化や価値創造の手法が限界を迎える中で、AIを導入すれば新しい次元の効率化や価値創造が可能になると信じていました。それが想像以上にさまざまな分野に波及し、予想外の効果を生んでいるのを目の当たりにして、私自身も驚いています。
G検定がもたらす変化と社員の成長
“AIを「自分ごと」として捉えられない人を
マイノリティにしたかった”
-上場企業のトップがG検定を受験し合格している例は珍しいと思います。受験のきっかけを教えてください。
三谷氏 日本ディープラーニング協会専務理事の岡田隆太朗さんの講演に感銘を受けたのがきっかけです。自分が拝聴したのは金沢星稜高校でも有名な稲置学園での周年記念講演でした。次世代の若者たちの真剣な眼差しに、ある種の焦りを感じたこともあって、「自分も勉強しよう」と思い立ちました。
-お忙しい中、どのようにして勉強と実務を両立されたのでしょうか?
三谷氏 「この知識が実務の中でどのように役立つのか」を想像しながら取り組みました。正直、テキストを最後まで読み切ることはできませんでしたが、実務を意識して学んだことで結果的に合格につながったのだと思います。
ーどのぐらいの社員の方がG検定に合格しているのでしょうか。
三谷氏 当社では、常勤役員の100%がG検定に合格し、社員では単体で75%、グループ全体で日本人社員の約55%が合格しています。現時点でその知識を業務で活用できている社員は限られていますが、まずはAIに対する基礎的な理解を持つことが重要です。社内の文化を築くために資格取得を奨励しているんです。社員全体でAIを活用できる文化を整えることで、組織全体が新たな価値を創出する基盤を築いています。
-情報通信総合研究所が2024年11月に発表したアンケート調査によると、従業員数1000人以上の大企業でも、生成AIを導入・検証している企業の割合は3割にとどまっており、ノウハウ不足や正確性の確認の難しさが課題として挙げられています※1。
そのような中で、三谷産業では社内での活用事例を各種会議体で共有し、さらにオンラインを通じて社外にも積極的に発信しています。こうした取り組みを通じて社員教育を推進し、全社的な生成AIの導入を実現しています。社員にG検定取得を奨励する背景には、どのような意図があるのでしょうか?
三谷氏 社長である私が取得したことで、社員に「自分も挑戦してみよう」と思わせる動機付けになったと感じています。私には、「AIを自分ごととして捉えられない人がいてもいいけど、できればマイノリティにしたい」という考えがありました。G検定に合格することで、社員はAIについて一通りの知識を持っていると認識されるようになります。そして、まだ取得していない人に対して、「君、G検定まだ取ってないの?」という空気が生まれる。そうなると、基礎教養としてAIを学んでいない人や興味がない人がマイノリティになっていくんです。決して「AIに詳しい人を増やすこと」が目的なのではなく、重要なのはAIを理解しない人や興味のない人が、AIを活用して新たな価値を創出できる人を組織の中で邪魔しないことだったんです。
- 採用にも影響はありましたか?
三谷氏 これから5年、10年後には、AIがあることを前提とした発想が当たり前の時代がきます。しかし、古い働き方やツールに縛られた職場では、ギャップに失望して離職する可能性があります。さらに、既存社員がAIに拒絶的な態度を取れば、新しい世代の可能性が閉ざされてしまう。そうした未来を避けるため、環境を整える必要があると感じています。
AIを歓迎する文化は、採用にも良い影響を与えます。AIに詳しい社員を「救世主」として歓迎する姿勢が理想です。一方で、「AIなんて仕事では使えない」と否定的な社員には、「それはおかしい」と指摘できるような環境を作りたい。そうした場が、社員の学ぶ意欲を引き出し、前向きな成長につながると考えています。社員はAIの取り組みにおいては、自分たちがトップランナーであるという実感を得ながらやっていると思います。それは「働きがい」につながっているのではないでしょうか。

社員の働き方における変化
-AI活用において、社員の意識や働き方にはどのような変化がありましたか?
三谷氏 以前は「AIやコンピューターが魔法のように何とかしてくれるでしょう」といった漠然とした期待を抱く声が多かったんです。例えば、統計データを分析して未来予測をするシステムを導入する際も、漠然とした希望が先行していました。でも、今では社員がAIの仕組みを基礎教養として理解するようになり、曖昧な期待感がなくなりました。
現在では、AIを活用したい部署が課題やニーズを明確にし、それに基づいた具体的な提案を出してくれるようになっています。また、情報システム事業部のメンバーも単なるサポート役にとどまらず、パートナー同士のような関係性で協力しながら、実現可能なプロジェクトを進めています。このような変化は、AIを企業文化として取り込むための重要なステップだと感じています。
次なる挑戦:AIと企業文化の融合
-これまでの取り組みを通じて見えてきた課題や可能性について、どのように考えていますか?
三谷氏 これまでの取り組みは第一段階に過ぎません。今後は、各部署がAIを活用して独自のイノベーションを起こし、部門間の連携をさらに強化することを目指しています。AIを使いこなすだけでなく、新たな価値を創出し、それを企業文化として根付かせることに注力していきたいと考えています。
後編では、三谷産業が取り組むAIを活用したプロトタイプ開発の具体例や、それによって生まれる新しい提案プロセスの変革について、三谷忠照社長にお話しいただきます。また、AIと人間が共存する未来に向けた展望についても語っていただきます。
※1 出典: 株式会社情報通信総合研究所「企業における生成AI活用の格差浮き彫りに -規模別・業種別の利用状況・課題と今後の展望-」
https://www.icr.co.jp/publicity/5135.html