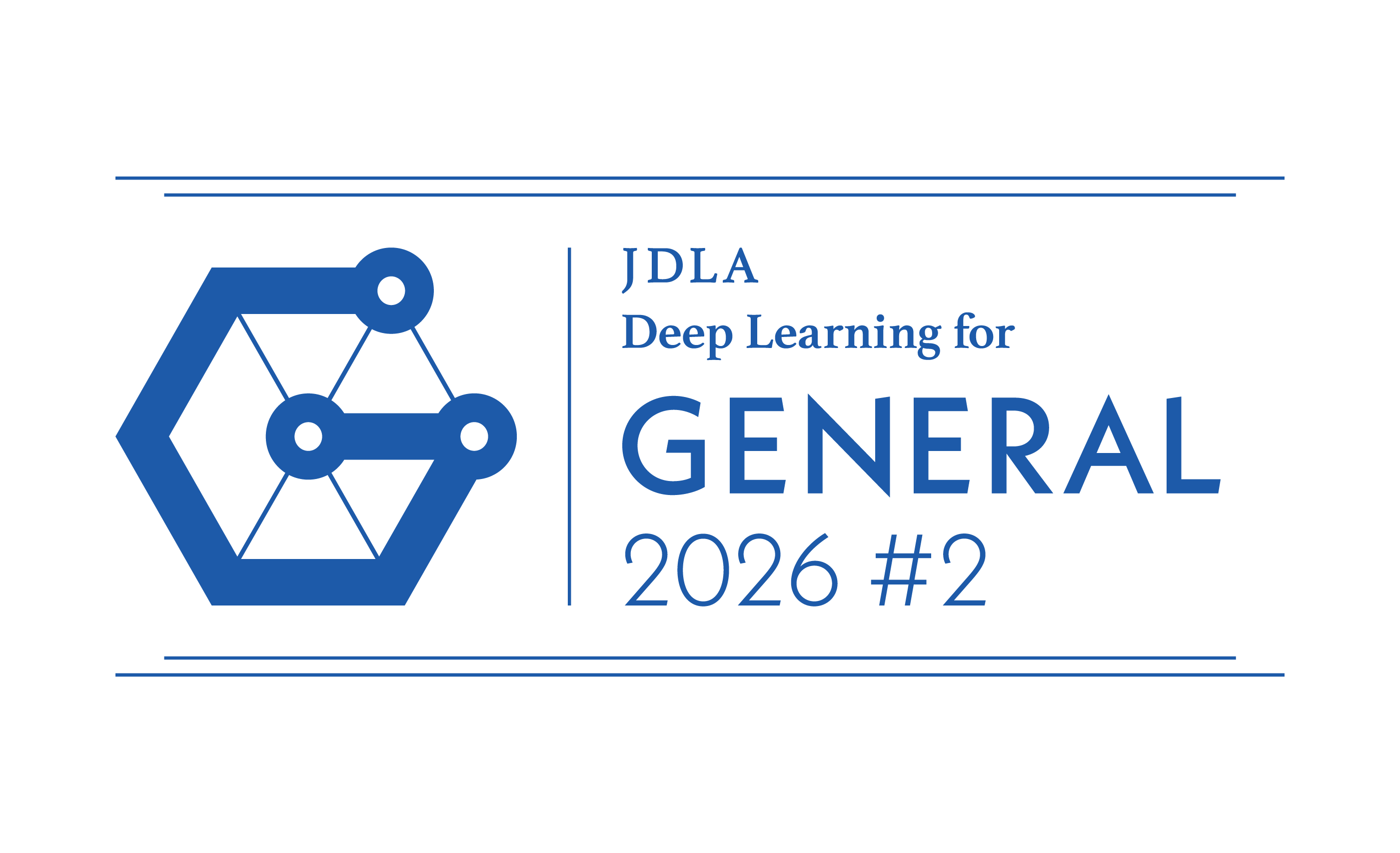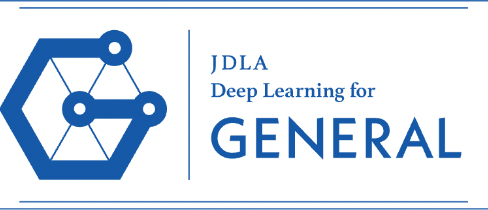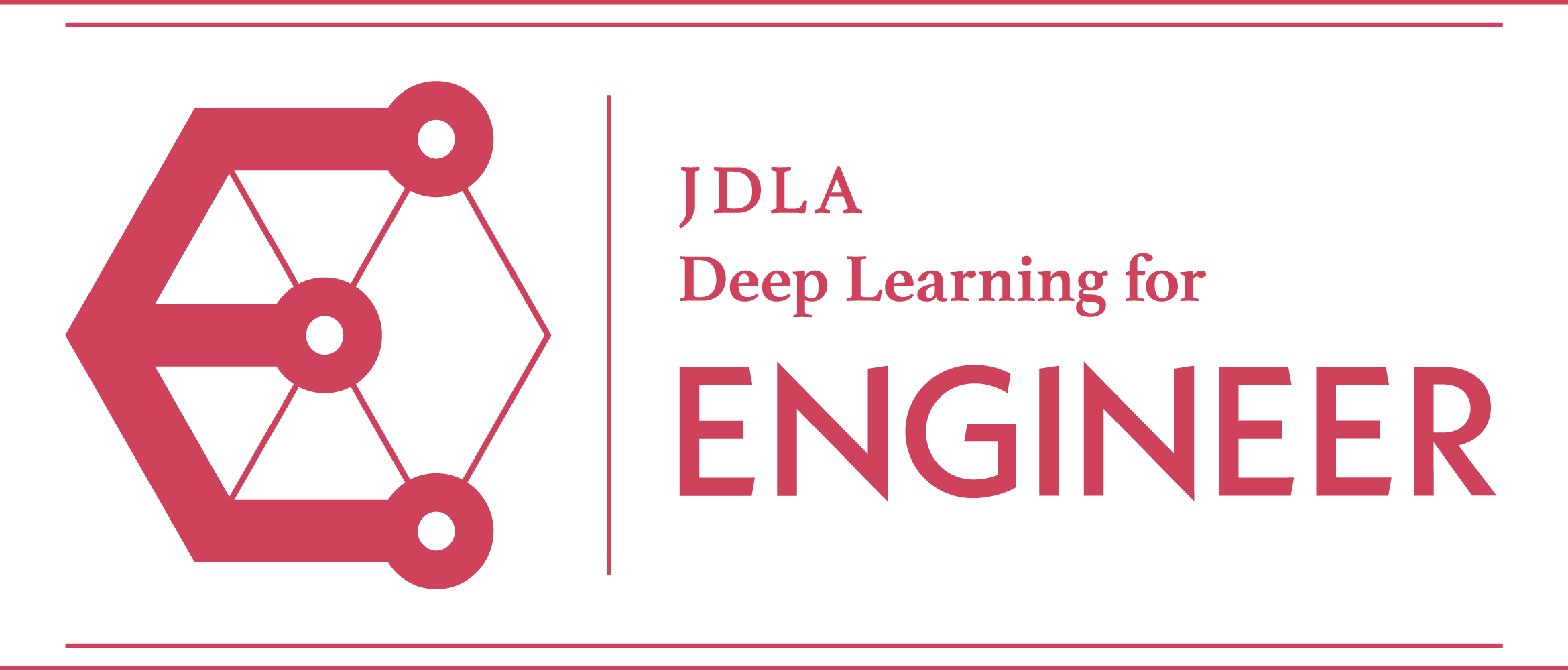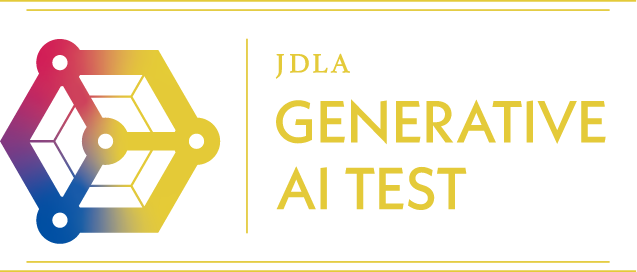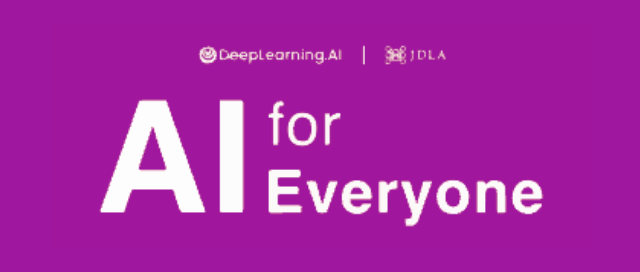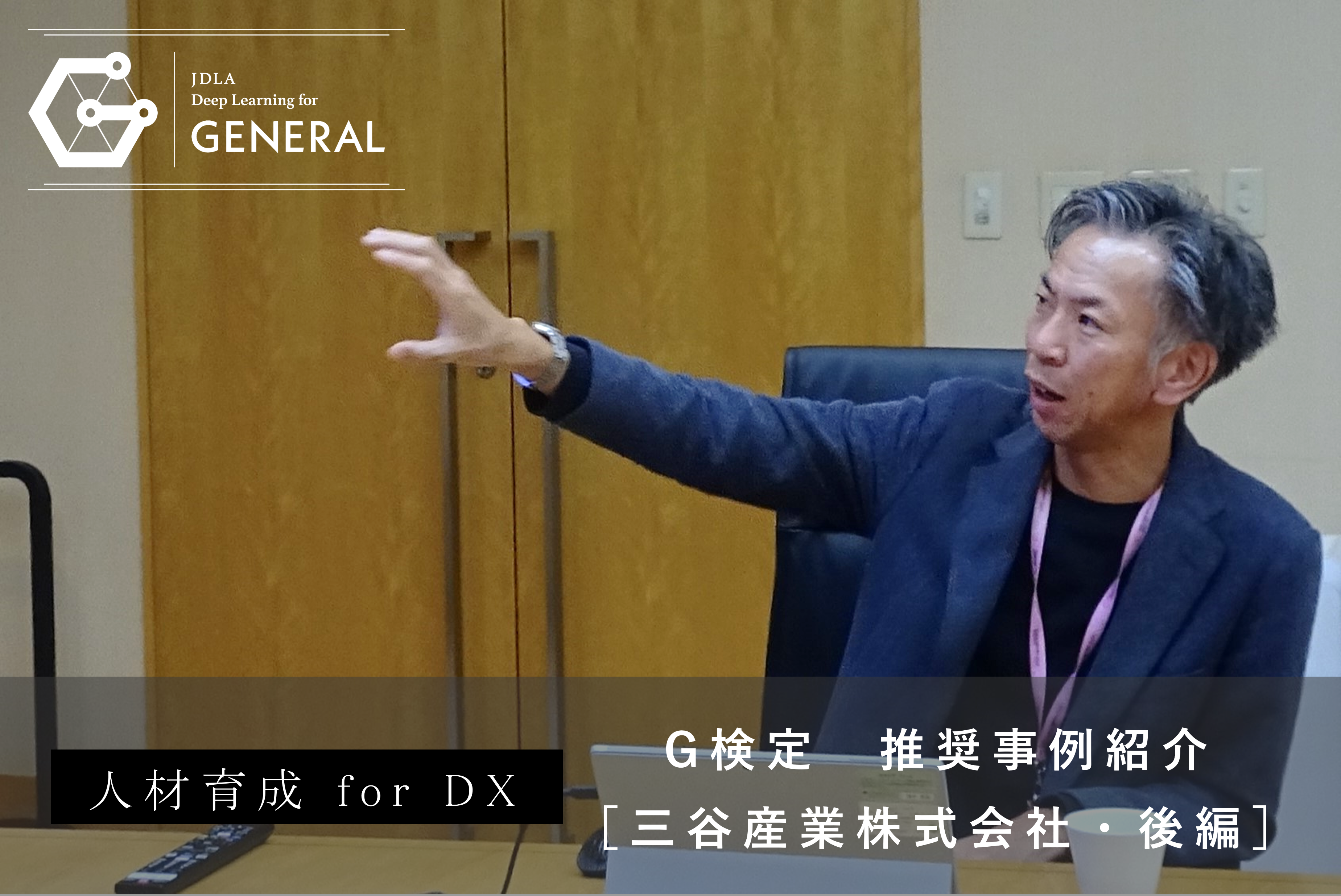
前編では、2023年を「AI元年」と位置付けた三谷産業の経営改革について紹介しました。三谷産業では、三谷社長自らG検定を取得し、トップダウンで社員に取得を奨励した結果、AIを「自分ごと」として捉える文化が根付き始めています。これにより、AIを用いた業務効率化や発想力の向上といった効果が生まれました。
AI活用の取り組みとプロトタイピングを活用したビジネスモデルの進化について、三谷社長と情報システム事業部 ソリューション企画部 部長の酒井 繁高氏にお話しを伺いました。
プロフィール:
三谷産業株式会社 代表取締役社長
三谷 忠照氏
三谷産業株式会社 情報システム事業部 ソリューション企画部 部長
酒井 繁高氏
AIで広がるビジネスの可能性
-どのようにして社員のAI活用のアイデアを形にしていますか?
酒井氏 G検定の学習を通じて、社員が業務の効率化や合理化を提案できる仕組みを導入しました。これまでに業務効率化に役立ちそうなテーマを73件提案してもらい、その中から18件を選びプロジェクトを進めています。

三谷氏 例えば、自動車部品の目視検査を自動化した外観検査機は、その一例です。カメラとAIを活用して高精度な検査を実現し、効率が大幅に向上しました。この技術は、社内だけでなく同業他社や新規顧客からも注目を集め、新たな事業機会の創出につながっています。
プロトタイピングがもたらす新たな価値
“プロトタイプが生み出すワクワク感。
思いがけない発見がそこに生まれる”
-AIを活用することで、提案や製品化プロセスにどのような変化がありましたか?
三谷氏 G検定合格に向けた学習の成果として、社員の発想も広がりました。具体的なアイデアを基に、「これを自社の事業に掛け合わせたら、こんな製品が作れるのでは?」といった形で、より実践的で精度の高い提案が増えています。こうした変化が、社内での業務効率化や新しい価値創造のきっかけになっています。
また、以前はお客様に対しても、提案書を作成してからご提案し、製品化を進めていましたが、今ではプロトタイプを基に、お客様と具体的な話を進めるスタイルに変わりました。これにより、システムの提案から稼働までのプロセスがスムーズになり、スピード感が大幅に向上しています。
例えば、キッチンのデザインを生成するAIのプロトタイプでは、「釣りが好き」という情報を入力すると、魚を捌くスペースを広めにしたキッチンデザインがリアルタイムで生成されるかもしれません。プロトタイプが顧客のインスピレーションを掻き立て、新たなアイデアが次々と生まれる仕組みを作っています。
-プロトタイプ開発がビジネスモデルにどのような影響を与えましたか?
三谷氏 従来のシステム開発では「納品」をゴールとしていましたが、ことAI活用に関しては、まずプロトタイプを提示し、お客様に使っていただきながら対話的に修正を繰り返します。その過程で、AIの精度や機能が高まっていくのを取り込んでいく、といったようなプロセスが中心的な考え方となっています。要件定義をしっかり作りこんでからシステム開発を行う「システムインテグレータ」としての存在から、お客様の会社における実質的なCDO(Chief Digital Officer)、これを当社では「バーチャルCDO」と定義して顧客と共創する新しいビジネスモデルが確立されつつあります。具体的には、システム開発やそのための要件定義に対して莫大な費用をいただくのではなく、お客様とともに行うプロトタイピングを月額契約していただく形で、バーチャルCDOサービスのサブスクリプション化が実現しています。
また、AIによる取り組みがきっかけで、これまで接点のなかった他事業部のお客様や新規顧客からの問い合わせが増えました。「AIについて詳しく話を聞きたい」といった依頼や、お取引させていただいている部門とは違う部門の方々との関係強化など、事業全体の顧客基盤を広げる成果が出ています。
「喋るエビ」プロジェクトのユニークな試み
-プロトタイプを活用した具体的な取り組み事例を教えてください。
三谷氏 最近のプロトタイピングの例として「エビの養殖プロジェクト」があります。高級エビの陸上養殖の可能性を模索するものですが、生育するエビを取り巻く環境データをセンサーで収集しそれを自然言語に変換し発信する仕組みを作りました。「今日は天気がいいエビ」「暑いエビ」のように、まるで生育中のエビが喋っているかのようなユニークな試みです。
この技術は養殖分野に留まらず、工場の生産状況や品質管理、営業情報など、さまざまなデータを自然言語で表現する可能性を秘めています。この仕組みを「ABI(Artificial Business Intelligence)」と名付け、AIを活用した新しいBIツールとして進化させています。ユーモラスな偶然ですが、「エビ」のプロジェクトから「ABI」が生まれたというわけです。
こうしたプロジェクトが実現したことには非常に満足しています。データを自然言語に変換するというアプローチは、通常のマルチモーダル技術とは異なる独自の可能性を持っており、とても興味深い挑戦だと感じています。
また、ビジネスへの転用可能性が見込まれる当社のプロトタイピング事例を「三谷プロトタイピングポートフォリオ」として公開しており、社内外に提案する活動を広げ始めています。
AIと人間の共存を目指して

楽しい、すごいと感じる瞬間を仕事の中で大切にしたい」と三谷氏
-ありがとうございます。最後に、AIの進化が進む中で、私たち人間の役割はどのように変わっていくとお考えでしょうか?
三谷氏 AIは進化を続けていますが、人間の価値が失われるわけではありません。たとえ自動運転の技術が発展しても、タクシードライバーの業務は運転だけではありません。心を込めてタクシードライバーという仕事ができる人がいるかぎり、運転席に人が座って接客することも許されてほしい。働くことは労苦でもあるが喜びでもある、と言うと日本的価値観が過ぎるかもしれませんが、すべての仕事をAIや機械に置き換えることを理想とするよりも、人とAIが役割分担をし直して共存する社会の方が幸せだと思います。私たちの挑戦は、AIと人間の役割をしっかり見極め、それぞれの強みを生かして新たな価値を創ることです。
AIは単なる工数削減の手段ではなく、ウェルビーイングを実現するためのツールだと思っています。「楽しい」とか「すごい」と感じられる瞬間や、人間らしい努力が生きる場面を仕事の中で大切にしたい。そのために、AIをどう活用していくかが重要だと考えています。