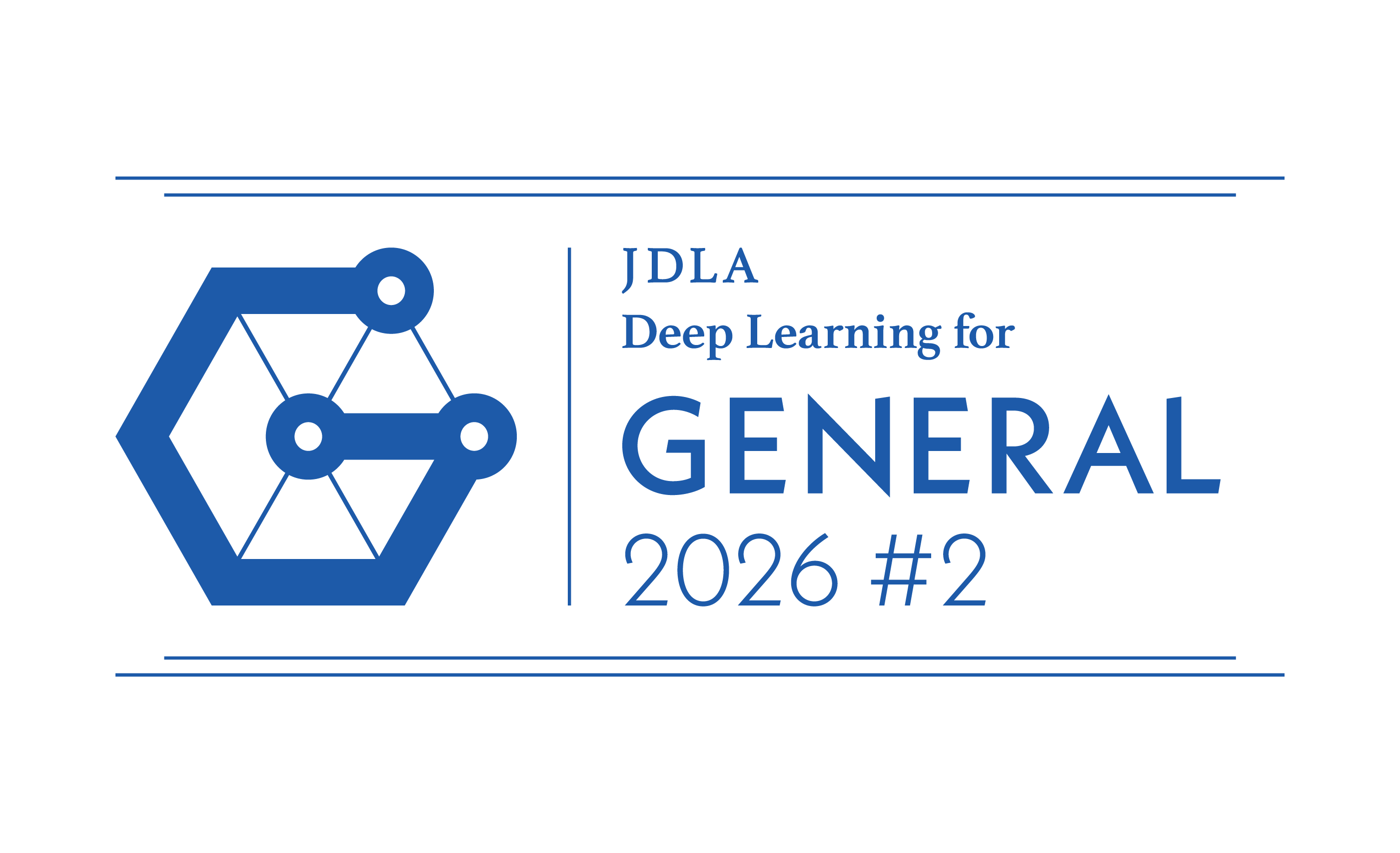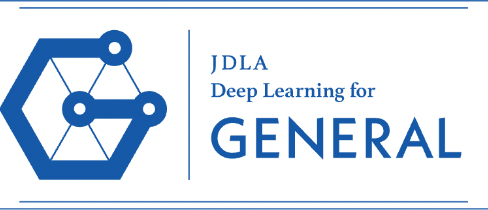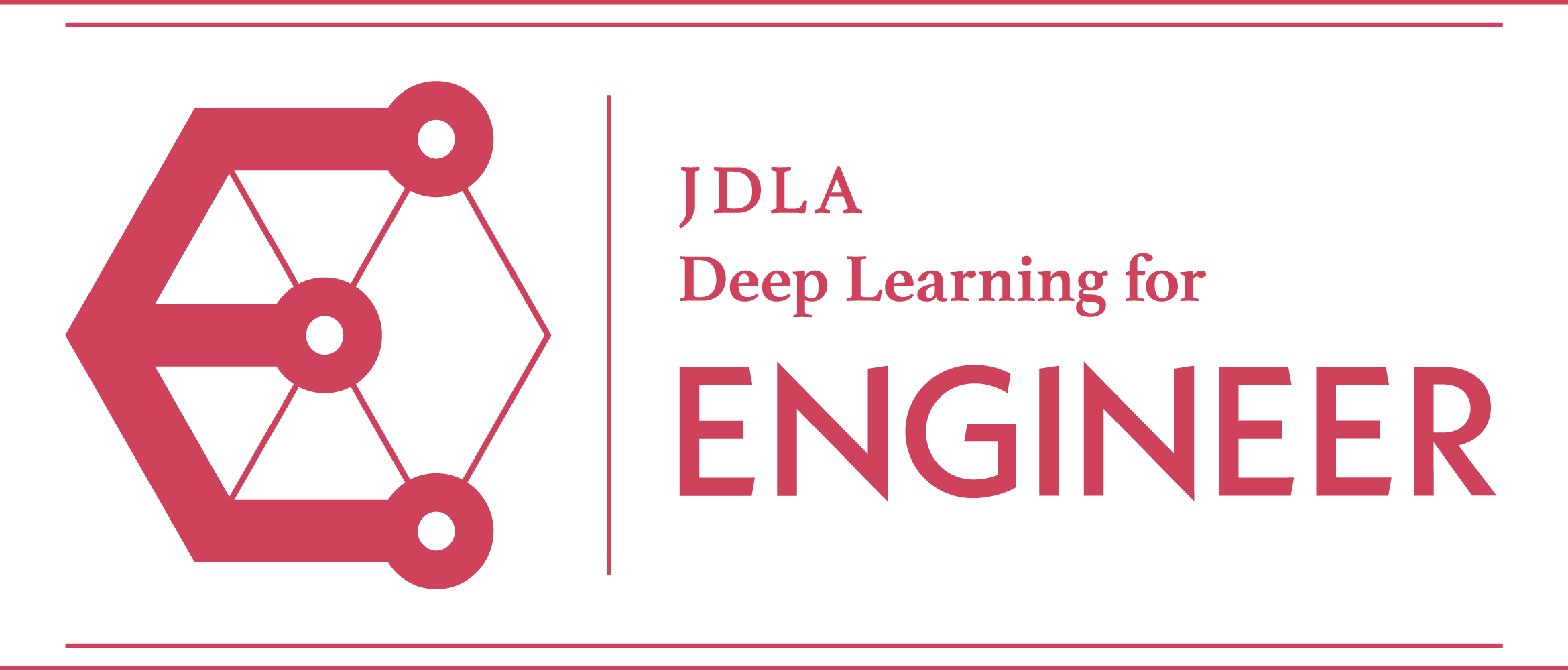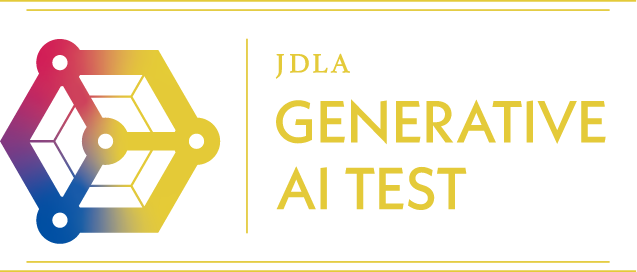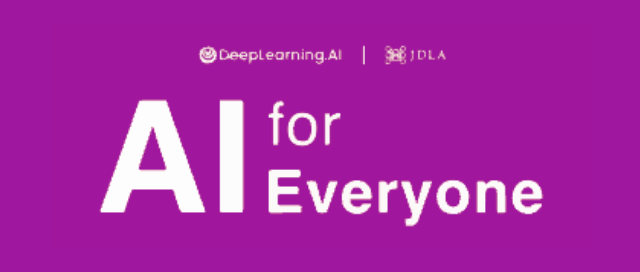[G検定・E資格 合格者インタビュー vol.24]
18年間、自動車の振動騒音開発に必要な計測現場というアナログな世界で活躍してきたトヨタ自動車の奥田賢さん。自学自習でプログラミングを習得し、G検定とE資格を取得。社内DX推進のキーパーソンへと変貌を遂げ、DXコミュニティの運営や社内のAI開発などに取り組んできた。資格取得を経て、奥田さんの世界はどのように変化し、どんな成長を遂げたのか?その熱い想いと挑戦の軌跡を聞いた。
【ポイント】
・18年間の振動騒音開発で感じたデジタルへの悔しさや危機感をバネに、孤独な中で自学自習をスタート。
・部内のDXを推進するチームに抜擢。G検定・E資格を取得しDX推進の立役者に。
・部長クラスを巻き込みながら社内DX推進コミュニティ「G-IT塾」を立ち上げ。約1年で1600人規模にまで成長。
・E資格で得た知識を活かし、スマートレジ、異常検知システムなど、AI開発の実績を重ねる。
G検定・E資格 合格者プロフィール

G検定 2021 #1 合格
E資格 2021 #2 合格
奥田 賢 氏
トヨタ自動車株式会社 車両技術開発部 デジタルクロスファンクションチーム
デジタルで悔しい思い…18年間の“泥臭い”開発経験からDX推進へ
――はじめに、自己紹介と現在の業務内容について教えてください。
奥田:トヨタ自動車の車両技術開発部デジタルクロスファンクションチームに所属し、2300人の部員を対象としたDX推進やAI・データサイエンスの活用促進、データサイエンス教育の講師などを担当しています。高校卒業後の2002年に入社して以来、約18年間は振動騒音開発に携わっていました。振動騒音開発とは、自動車の振動や騒音を抑制し性能向上につなげるため、計測器を使って多くのデータを取得・分析していく仕事です。
――デジタルクロスファンクションチームとは、どのようなチームなのでしょうか?
奥田:車両技術開発部には、振動騒音のほかにも熱燃費、空力、運動性能など、車の性能に関わる17の試験課があります。デジタルクロスファンクションチームは、これらの試験課からデジタルに強い人材を集めたDX推進の専門部隊です。発足は2020年11月、世間でDXやデジタル化が叫ばれ始めた頃でした。車両技術開発部もこの波に乗り遅れないようにと、各課で孤独ながらも自学自習でデジタル化を推進していたメンバーが集められました。メンバーは私を含め10人程度です。
――奥田さんがデジタルクロスファンクションチームに抜擢されたのは、職場でデジタル推進や自学自習をされていたからだったのですね。“孤独”ながらも、その活動を始められた理由や背景にあった思いを教えてください。
奥田:18年間「車を走らせて評価してなんぼ」の泥臭い仕事をしてきましたが、デジタルで悔しい思いをしたのがきっかけです。アナログな評価をするにしても、我々が使う計測器にしても、どこでも壁を感じるのがデジタルだったんです。
振動騒音開発では、何千万円もするような計測器を使用しますが、計測器の中身を詳しく見てみると実はプログラミングである程度再現できるのではないかと気づいたんです。さらに、新しい試験を考案する際にも、プログラミングやデジタル技術が不可欠。ちょうど自動車業界が100年に一度の大変革期と言われていた時期でもあり、「学ばなければ何もできないぞ」と奮起。妻に頭を下げてMATLABのライセンスなどを購入し、自宅学習の日々が始まりました。当時は情報も少なく、相談できる人もいない、まさに孤独な戦いでした。
その後、2000万円もする計測器が、MATLABを勉強したことで自作できるようになりました。自分の技術を高めれば、既製品を買うよりも安く、そして自分のやりたいことにカスタマイズした計測器を作れる。プラスアルファを生み出せるデジタル技術の可能性を感じました。そして、振動騒音試験課で最後の半年間、職場のデジタル化推進を担当したことがきっかけで今のチームに声をかけていただきました。
資格取得が「武器」に。説得力と共通言語を手に入れる
――G検定やE資格を知ったきっかけについて教えてください。
奥田:実は、どちらの資格も存在をほとんど知りませんでした。デジタルクロスファンクションチームに異動してすぐに、尊敬する上司の岩堀嘉仁さんが E資格の取得を目指していると聞き、内容もよく分からないまま「この人が取るなら自分も取ろう」と受験を決意。そんな中、後輩たちがG検定に興味を示してくれていることを知り、彼らを応援するためにも「ついでに」G検定も受験。E資格の勉強中にG検定も取得したので、岩堀さんには驚かれました(笑)。

――先にE資格の方から学習をスタートされていたのですね。資格取得を目指す決め手は何だったのでしょうか?
奥田:デジタルクロスファンクションチームの他のメンバーは、デジタルに精通していてマニアックな人ばかり。その中で唯一アナログな仕事ばかりしてきたのが私で、他に保有しているIT系の資格もなく、ゼロから、むしろマイナスからのスタートでした。
2300人もの部員を対象にDXやAIを推進していく中で、自分の言葉に重みがないと痛感する場面も多々ありました。基礎的なプログラミングやDXの概念を教える講師をしていたときも受講生が理解しているか不安でしたし、予算獲得のために上長を説得する際にも自信が持てませんでした。資格を取得することで、自分の言葉に説得力を持たせたい、自分のバックボーンとなる武器が欲しい、という思いがありました。
――E資格とG検定の学習方法、学習期間や学習時間について教えてください。また、学習を進める中で苦労した点はありますか。
奥田:E資格の認定プログラムのほかに、黒本と言われる問題集、ディープラーニングの入門書である「ゼロから作るDeep Learning」の2冊を徹底的に読み込みました。実践的な技術を身に着けたいと思い、AIモデルを自分で試すことに時間を費やしていたので、平日4~5時間、休日6~7時間、合計1050時間ほど勉強しました。G検定の勉強期間は、3週間程度でした。

元々、振動騒音開発をしていたのもあり物理や数学は好きでしたが、教科学習的な内容の理解に苦労しました。いくら問題を解いても、模擬試験で良い点数を取れても、真の理解に到達していないと感じる部分がありました。
――平日も休日もそれだけ学習時間を捻出するのは大変だったかと思いますが、モチベーションを維持する秘訣はありますか?
奥田:家族には迷惑をかけてしまったかもしれませんが、学習時間の確保には苦労しませんでした。学生時代は勉強嫌いで全然勉強していなかったので、その反発かもしれないですね。子どもに「勉強教えて」と言われても、どう教えたら良いのか分からなかったですし、講師としても「私が何を教えられるんだろう」という変な恥ずかしさもありました。“社会人デビュー”じゃないですが、大人になってからとにかく勉強を頑張り始めた感じです。
モチベーションも特に落ちることなく学習を続けられました。上司(岩堀さん)が一緒に受験していたので、密に情報共有をしていましたし、さぼれないプレッシャーという意味でも心強い存在でした。
――G検定やE資格の受験を検討している人や学習中の人に、アドバイスはありますか?
奥田:「(資格取得したら)世界が変わりますよ」と伝えたいですね。勉強がつらくなったり、学習時間が取れないという悩みもよく聞きますが、そういう時は「資格を取った後に何がしたいか」を妄想するのがおすすめです。私の周りにも、資格取得後に燃え尽きてしまう人がいるのですが、「上司を説得したい」「後輩に教えるときの一助になる」など、何か一つ軸を持つことが大切だと伝えています。
――奥田さんご自身は、資格取得によって世界は変わりましたか?
奥田:大きく変わりました。実務面でいうと、予算獲得がスムーズになったことがひとつです。大きな会社なので予算担当部署のメンバーが多い為、調整に苦労するのですが、E資格やG検定があることで、説明に説得力が増したと実感しています。なかなか買えなかった高性能PCが購入できたのも、まさに資格のおかげだと思っています。
日常的なところで言うと、以前はデジタルに詳しい後輩から「奥田さんはデジタル詳しくないよね~」と言われていたんですが、資格取得後は「奥田さんが講師をやっている!」「奥田さん、いつの間にか社外の〇〇さんと親しくなっているぞ!」と、変わりました(笑)。マニアックな専門用語も分かるようになったことで、コミュニケーションも円滑になりました。「この子たちはこんなに苦労して、頑張ってやっていたんだな」と仲間の努力も理解できるようになり、嬉しかったですね。
シニア世代の活躍も後押しするDX推進コミュニティ「G-IT塾」
――社内では、他にどのようなDX推進の取り組みがありますか?
奥田:トヨタでは、ボトムアップ型のDX推進のコミュニティ活動が盛んです。例えば、Microsoft Power Platformでノーコード・ローコードによる市民開発(工場現場で働く担当者自らがプログラムを開発)に取り組む9000人規模のコミュニティなどがあります。
――奥田さんと岩堀さんも、DX推進コミュニティ「G-IT塾」を立ち上げられていますね。立ち上げの経緯について教えてください。
奥田:G-IT塾は、車両技術開発部内のDX推進を加速させるために立ち上げました。私たちの部署がDXで遅れを取っているという危機感と、他の部署に追いつきたいという思いからです。発足当時は、「デジタル化推進やプログラミング活用をどうすればいいか分からない」といった質問が部署内に散在していたので、質問を一元管理し、詳しい人が集まって問題解決できる場を作りたいと考えました。
―― G-IT塾の内容や活動頻度、参加人数などを教えてください。
奥田:メインコンテンツは隔週で開催する30分ほどの「プチ講座」です。チャットで寄せられた質問や、今後起こりそうな問題を先取りしてテーマに設定するなど、タイムリーな内容を提供しています。講師は毎回変わり、普段一緒に仕事をしているメンバーが中心です。年末年始などの大型連休前には部長や上長に登壇してもらい、1時間ほどの拡大版講座を開催することもありました。

1回の講座には平均100人ほどが参加し、活発な議論が交わされます。参加者は車両技術開発部以外からも集まり、年齢や役職も新入社員からベテラン、管理職まで様々です。普段は交わらない人たちが集まり交流を深めているのもG-IT塾の特徴ですね。
――発足から1年ほどで1600人もの人が集まったそうですね。大きなコミュニティに成長できたポイントについて教えてください。
奥田:まさかこんなに大きくなるとは思っていなかったんです。普段はなかなか話しかけられない部長クラスの方々に発起人になっていただき、「部長にプログラミングさせてみた」といったコンテンツを作成したり、社内インフルエンサーを巻き込んでイベントを盛り上げたりしました。一気に増えたというよりは、地道な教育コンテンツの積み重ねですね。

私の経験では、理解のある方を巻き込むことで物事がスムーズに進むことが多いです。私一人では難しい場合は、社内で顔が広く、誰とでも気軽にコミュニケーションが取れる岩堀さんに協力をお願いしました。通常、300人規模のイベントを開催する場合、様々な手続きを経て1年以上かかることもありますが、部長クラスの方を巻き込むことで、1カ月、あるいは1週間ほどで開催できるようになりました。
――G-IT塾の参加者からの反響や、成果についてはいかがですか。
奥田:私たちの組織は細分化されていて、部署間の壁も厚く、一人ではなかなか進められなかったことも、部長のお墨付きもある「G-IT塾のおかげでスムーズに進んで助かる」という声をよく聞きます。「プログラミングを始めたい」「部署の小さな仕事を改善したい」といった些細なことも、始めるのにハードルが高い部署もあります。チャットで気軽に質問を投げれば誰かが必ず解決してくれる、G-IT塾はそんな場所を目指していたので、大きなプラスになれたかなと思っています。
G検定やE資格の取得についても同様です。職場に学習仲間がいなかったり、実際に「そんな資格を取って何の意味があるんだ」と言われしまった人もいます。せっかく頑張ろうとしているのに頑張れない状況は悲しいし、無くしたい。G-IT塾で仲間を見つけ、学習を後押しできる環境がコミュニティの良さだと思っています。私自身もMATLABを買って孤独に勉強していた頃を思い出し、そうならないようにという思いもありました。
――「自分はデジタルなんて全然ダメ」「興味ない」という方も一部いると思いますが、そういう方々へのモチベーションアップは工夫されていることはありますか?
奥田:私たちも長年アナログな仕事をしてきたので、そういう方の気持ちもよく分かります。G-IT塾にも、「デジタルはわしゃやらん!」と言っている方もいました。でも、G-IT塾には来てくださっているので、何かしら興味を持ってくださっているはず。なので、Udemyなどの学習機会は均等に提供するようにしましたし、質問にも決してないがしろにしないようにしていました。
実際に話を聞いてみると、実はデジタルに興味津々で、こっそり勉強していたという方も多いんです。社内には「プログラミングを60歳から始めました」「おじいちゃんになってから勉強してみたらハマっちゃった」という人もいて、こういう方々はまさに宝だと思っています。そういう方こそ職場で話す相手がいなかったり、孤独を感じていたりするので、積極的に情報を提供したり、後でこっそりチャットで話を聞いてみたり。すると、堰を切ったように話してくれるんです。「これは何なんだ!」と文句を言っている人ほど、実は聞いてほしいことがたくさんあるんですよね。そこをうまく刺激するようにしていました。
スマートレジやAIタレントの開発にも挑戦
――E資格で得た知識を活かし、AI開発にも取り組まれているそうですね。
奥田:E資格の学習時に初めて画像認識AIモデルに触れ、スマートレジの開発に取り組みました。近くの部署の困りごとを解決するために、バーコード管理されていた物品の貸し出し管理を画像認識で行う「万能スキャン」を開発。このシステムは4部署に展開され、画像学習方法に関する特許も取得しました。その後、異常検知に興味を持ち、トヨタの工場で人間の目視検査をカメラに置き換えるプロジェクトに携わりました。
――画像生成AIを活用して、CM動画の作成やAIタレントの開発にも挑戦されているとか。
奥田:これも近くの部署からの相談がきっかけです。ある役職者の方が、年に何回も依頼される安全講話のコメント撮りが大変だという話を聞き、その方の写真やイラストからAIタレントを作成し、講話動画を作成しました。

奥田:今、力を入れて開発しているのはAIエージェントです。具体的には、人事評価をサポートするAIエージェントのほか、AIやデータサイエンスに関する問い合わせ対応や最新AI情報の発信を行う対話型エージェントの「AIトヨタ従業員」、属人化された業務や技術を日々の業務データと質問によって吸い上げるAIと引継ぎや問い合わせ対応を行うAIを並列駆動させることで、技術伝承を自立支援する「匠の技術伝承AIエージェント」の3種類です。すでに、職場では私たちの仕事を楽にしてくれる成果が出てきています。AIによる業務サポートは今後さらに重要性が高まると思うので、さらに技術を高めていきたいですね。
―― 最後に、描いているキャリアパスや、今後挑戦したいことを教えてください。
奥田:社内での大規模な開発は一段落したので、今後はデジタルクロスファンクションチームのメンバー、特に優秀な若手たちが活躍できる環境づくりに力を注ぎたいです。熱心に勉強していて数多くの開発をしているメンバーが輝けるように、裏方のエンジニアとしてサポートしていきたいです。彼らが「良い開発ができた!」と自信を持って言えるような職場にしていきたいなと思っています。