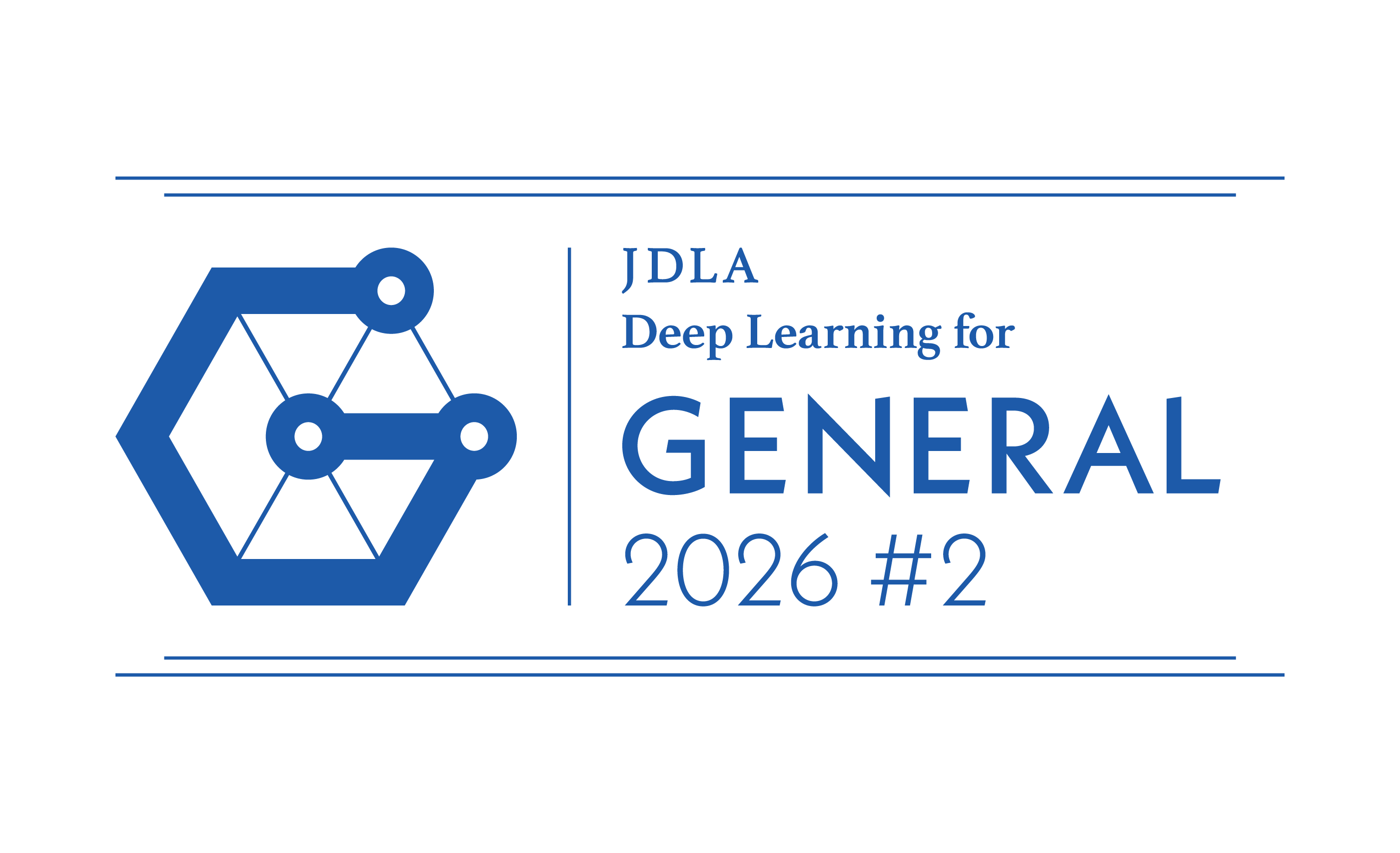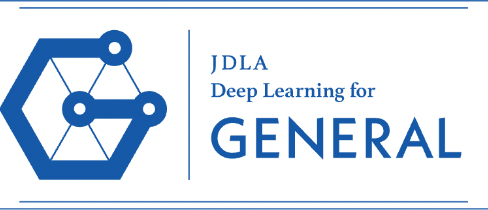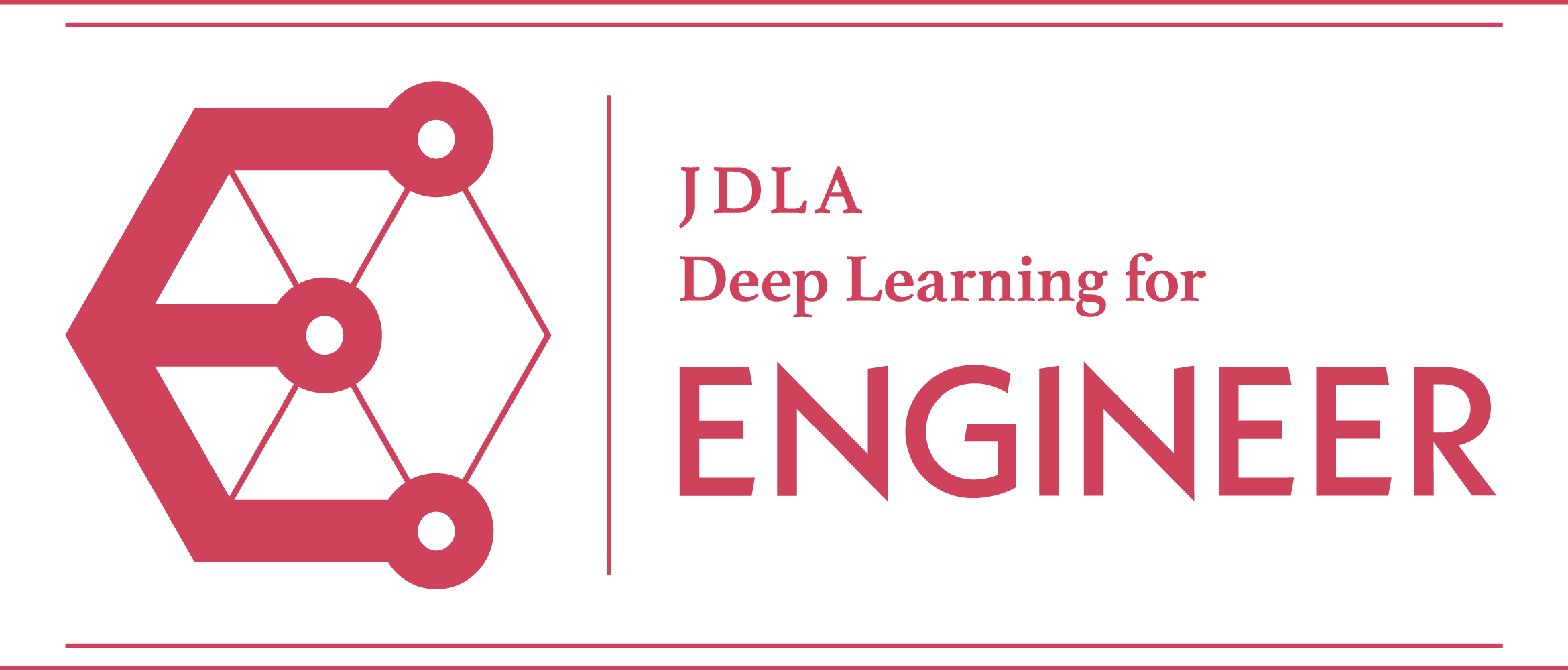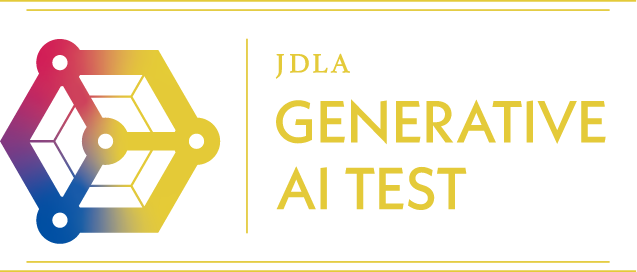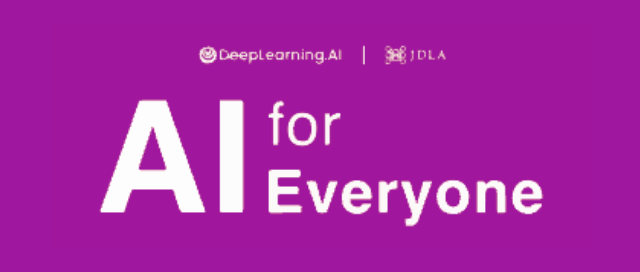[G検定・E資格 合格者インタビュー vol.25]
TOTO株式会社で営業支援ツールの活用推進やデータ活用人材育成を担う鈴木隆太郎さんは、G検定・E資格の両資格を取得し、技術部門から販売部門まで幅広い領域でデータ活用のエバンジェリストとして活躍している。資格取得をきっかけに社内勉強会を立ち上げるなど、AI人材育成のために精力的に活動してきた鈴木さん。AI人材育成や社内DX推進のヒントについて語ってもらった。
【ポイント】
・コア技術の開発からデータ活用のチームへ。講師としてデータ活用人材を育成していくためG検定を取得
・続けてE資格も合格し、AI知識を体系化。より自信を持った指導で人材育成に貢献
・販売部門への異動で新たな挑戦。営業担当者のデータ活用スキル向上を目指す
・今後の目標は販売部門のデータ活用の加速、そしてマーケティング分野への挑戦
【G検定・E資格 合格者プロフィール】
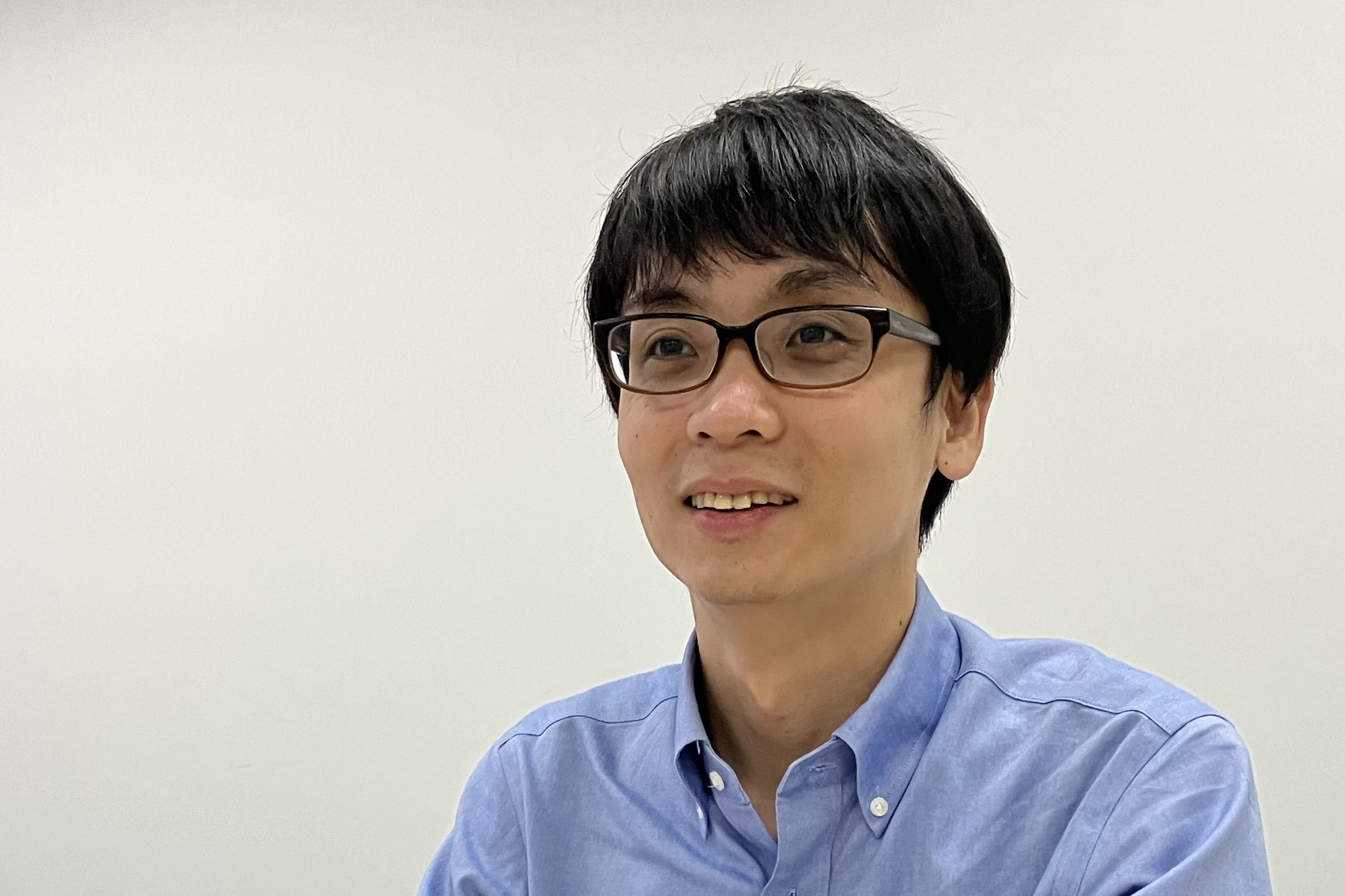
G検定 2020 #2 合格
E資格 2023 #1 合格
鈴木 隆太郎 氏
TOTO株式会社 販売統括本部 販売革新推進グループ
技術開発からデータ活用スペシャリスト、そして営業支援の最前線へ
――はじめに、これまでのご経歴と現在のお仕事について教えてください。
鈴木:2014年にTOTOに入社し、技術本部(旧・生産技術本部)で工場の原価管理を担当した後、CAE(Computer Aided Engineering)技術グループでコンピュータシミュレーションを用いた製造プロセスや不良発生のシミュレーションに携わっていました。2020年に立ち上がったデータ革新プロジェクト(現在のデータ革新推進室の前身)の初期メンバーとして参画し、データ活用やAI、統計解析などを実践的に行ってきました。2024年4月からは販売統括本部 販売革新推進グループに異動し、営業支援ツールの活用展開やデータ活用人材の育成に取り組んでいます。
――データ革新推進室とはどのような部署なのでしょうか?
鈴木:元々は、CAE技術グループ内でビッグデータ分析に取り組む一つのチームとして立ち上がり、チームに加わった時には、私を含め3人の体制でした。衛生陶器の工場での良品条件分析(複雑な形状の製品の製造条件を数値化し、不良率の低減を目指す)の取り組みが社内で高く評価されたことで、全社的なデータ活用推進の機運が高まり、プロジェクト化。そして正式な組織へと発展していったという経緯があります。
データ革新推進室の特徴的な取り組みが、部署横断でデータ活用人材を育成する「留学生制度」です。各部門から選出された社員を2年間、「留学生」としてデータ革新推進室に迎え入れ、データ分析の基礎スキル習得から、出身部門の課題解決のためのOJTまで、実践的なカリキュラムを通じてデータサイエンティストの基礎スキルを学びます。その後、留学生は元の部署に戻り、各現場でデータ活用を推進していく役割を担うのです。この制度は、ウォシュレットや浴室、キッチンなどの各事業部の技術系だけでなく、販売やサプライチェーンなどの部門からも参加者を募り、全社的なデータ活用人材の育成に貢献しています。私は留学生を技術的に支援する立場として、各メンバーへのアドバイスを行っていました。
――2024年4月から販売部門へ異動されたのは、どのような経緯だったのでしょうか?
鈴木:データ革新推進室時代から、販売・マーケティング分野でのデータ活用に大きな可能性を感じていました。会社としても販売部門のDX推進を強化していく方針があり、私自身もその領域で貢献したいという思いが強まり、異動を希望しました。
異動先の部署の具体的な業務としては、営業支援ツールの導入・定着支援、データに基づいたダッシュボード作成、営業担当者への教育などです。営業担当者がデータとツールを活用して、より効率的かつ効果的に業務を進められるよう日々サポートしています。
G検定・E資格取得でAI知識を深化させ、社内AI人材育成を推進
―― では、G検定を受験しようと思ったきっかけを教えてください。
鈴木:2020年にデータ革新プロジェクトが立ち上がり留学生をサポートする立場になって、AIに関する知見を深める必要性を感じたからです。元々は多変量解析などの統計をメインに扱うチームだったので、AIの専門知識を持つメンバーは限られていました。ただ、他部署からは「AIに詳しい人たち」とも思われているので、きちんと正しい知識をつけて教えていく必要がある。そこで、AIに関する体系的な知識を習得するためにG検定の受験を決めました。かねてから独学での学習を進めていましたが、知識の抜け漏れを確認する目的も兼ねていました。留学生の1期生でG検定の受験を希望する方が2人いたので、刺激を受けながら学習を進めることができましたね。
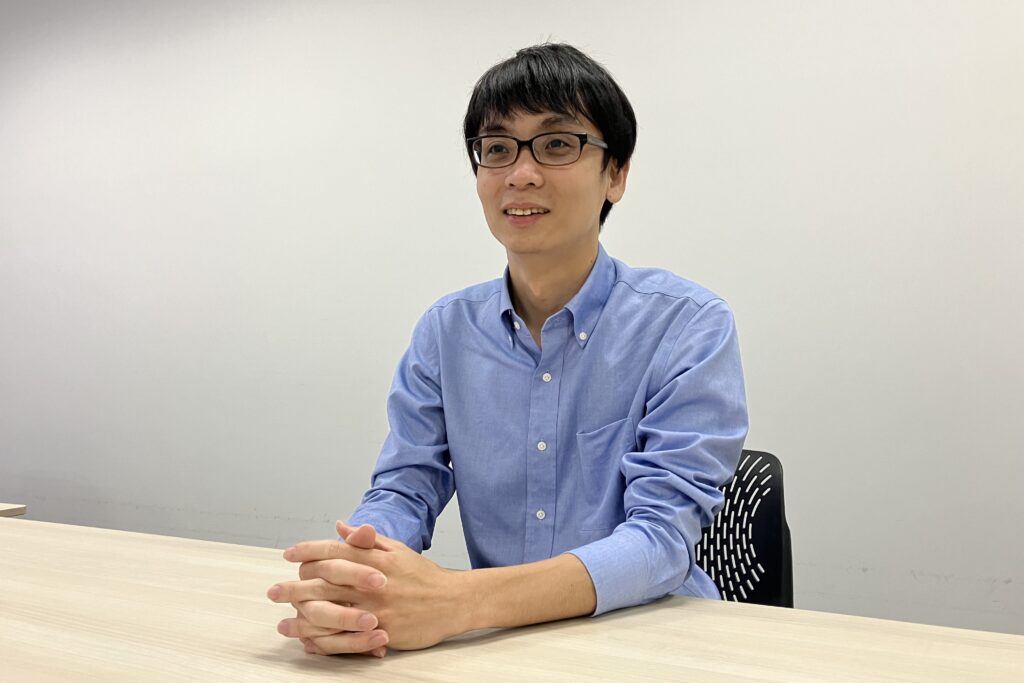
―― G検定合格後、E資格も取得されていますが、その理由を教えてください。
鈴木:G検定合格後、データ革新推進室内で機械学習の勉強会を立ち上げました。この勉強会は、留学生向けの教育カリキュラムに機械学習に関する内容が不足していると感じていたので、私と他の2人のメンバーが上司に提案して実現したものです。
ただ、テキスト作成や講義をするうえで、やはり知識の抜け漏れがないかが不安になり、E資格の取得を目指すことにしました。E資格の認定プログラム受講料と受験料の高さがネックになっていたのですが、上司に相談したところ会社から補助を受けられることに。それも追い風になりましたね。
――G検定とE資格の学習方法について教えてください。
鈴木:G検定については、以前から独学で勉強していたこともあったので、G検定対策の無料講座で不足部分を補完する程度でした。E資格は、スキルアップAIのオンライン講座を受講し、確認のために黒本を活用する、という感じでした。こちらも勉強会で最低限の知識は持っていた部分もあって、黒本をガツガツこなすというよりも、スキルアップAIの講座の内容を1個1個理解していくことを重視していました。
――学習で苦労した点はありましたか? 学習のモチベーションを維持する秘訣があれば教えてください。
鈴木:G検定では、AIの歴史や法律に関する分野はこれまで触れていなかった部分だったので、検定を通して学べたのは良かったですね。E資格の学習は範囲も広く大変でしたが、楽しみながら学ぶことができました。E資格で得た知識は、AI全般の理解を深める上で非常に役立ちます。現在実用化されているAI技術について社外のエンジニアとのコミュニケーションがスムーズにできるという意味でも、苦労した甲斐があったと感じています。
―― 資格取得によって、どのようなポジティブな変化がありましたか?
鈴木:講師として自信を持って教えることができるようになったと思います。G検定合格後には機械学習の勉強会立ち上げにもつながりましたし、E資格はそこで教える内容に間違いや漏れがないかの確認にもなりました。
社外での活動としては、JDLA認定プログラム合格者コミュニティ「CDLE」も参加し、CDLE福岡の運営にも携わらせていただいています。コミュニティ活動やSlackでの情報交換を通じて、社外の方々と交流ができたことも大きな収穫です。
意欲的な人を孤立させずに支え、データ活用の輪を広げる
――キャリア観においては、何か良い変化はありましたか?
鈴木:そもそも、CAE技術グループに在籍時、データ活用のチームに移った理由の1つが「データ活用でマーケティングを変革したい」という思いがあったためです。 というのも、当時シミュレーション技術で商品開発を支援する中で、「この商品はお客様が本当に求めているものなのだろうか?」という疑問を抱く瞬間がありました。もちろん、商品企画に関わる方々が必死に調べ考え抜かれた商品だったと思いますが、「お客様のニーズを捉えるには、もっとデータを活用できるはずだ」という漠然とした思いがずっと頭の中に残っていました。ただ、当時は全く異なる部門にいたので、それは夢のまた夢のことでした。

その後、データ活用のチームへの異動やデータ革新プロジェクトへの参加を経て、AIや統計に関する知識を深め、現在では販売部門のデータ活用推進という形で、当初の目標に近づいていると感じています。将来的にはマーケティング領域へのデータ活用展開にも挑戦していきたいです。
―― 今後、どのようなキャリアを描かれていますか?
鈴木:機械学習勉強会の講師は後輩に引き継ぎ、現在は販売部門の目指すDX像や人材要件定義から具体的な育成計画について、検討・推進中です。まずは、人材育成により販売部門内にDXが根付く土壌を作り、データに基づいた営業戦略の立案・実行を推進していきたいです。将来的には、マーケティング領域にもデータ活用を広げ、TOTO全体のDX推進に貢献していきたいと思っています。
――社内でデータ活用の人材育成を推進する際に、「私はそんなことできない」と学習に意欲的でない方も一定数いらっしゃいます。そのような方々のモチベートにおいて、意識されていることはありますか?
鈴木:私もとても試行錯誤しているところではあります。特に販売部門ではデータ活用に苦手意識を持つ方も多いです。まずは慣れてもらうところから始めようと思い、社内SNSでAI関連情報を発信したりしていますが、まだまだ課題は山積みです。
データ活用を推進する上でのポイントは、まずはデータ活用に意欲的な人を孤立させず積極的にサポートすることだと考えています。彼らが成功事例を共有することで、周囲の人にも興味を持ってもらうという戦略ですね。各支社に1人でもデータ活用推進のキーパーソンを育成できれば、「自分もやってみようかな」という人が増え、データ活用の輪が広がっていくと信じています。
これまでも“孤立させない”ための案として、Pythonを学ぶオンラインの勉強会の「Pythonもくもく会」を企画・開催していました。普段プログラミングとは直接関係のない部署や職種も含めた全社員が対象で、多いときは200人以上が参加していました。部門を超えた交流から新たな気づきを得たり、モチベーションを高めたりする機会をうまく作れると、良い風向きを作っていけるんじゃないかと考えています。